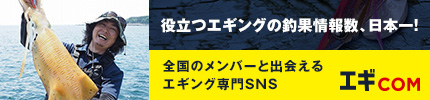最大で全長1mほどになるヒラメは、成長スピードが早く、1年で30cm、2年で50cmを超える。動かないエサには食いつかないといわれており、そのためルアーアクションが重要なカギとなる。
ヒラメのルアーフィッシング(入門者向け)

- 分 類カレイ目ヒラメ科ヒラメ属
- 学 名Paralichthys olivaceus
- 英 名Bastard halibut
- 別 名オオグチガレイ、テックイ、エテガレイなど
釣りシーズン ベストシーズン 釣れる
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
◆こんなところで釣れる

◯サーフを代表するルアーターゲット
ヒラメは砂や砂利の中に潜りエサを待ち伏せる性質を持つため、底質が砂や砂利の港湾部やサーフがメインフィールドとなる。
ヒラメは本来水深80m以上の深場を生息域としているが、春の産卵行動の前後に20m以浅のエリアに移動してくるものや、産卵に関係なくベイトが接岸する夏から秋にかけて沿岸域へと集まる個体もおり、サイズにこだわらなければほぼ一年中狙える。
なお、40㎝程度までの小型はソゲと呼ばれる。40㎝以上の正真正銘のヒラメサイズを狙うなら初夏ごろと秋から冬にかけてがベストである。
姿形から大人しく砂に潜みじっと潜んでいるイメージもあるが、ひとたびベイトが巡ってくるとボトムから水面近くまで浮上してくることもある。
底質は砂地、砂利、ゴロタがよく、完全な岩礁帯や藻が繁茂するような場所では数は見込めないが型が出る。淡水に強いわけではないがベイトを追って河口域にも姿を現すこともある。
◯日中のターゲット
ヒラメの一日の行動は人間によく似ている。夜間は深場でじっと休んでおり、日が昇りベイトの動きが活発になるとともに捕食のため動き出す。日中は浅場で捕食を続け、夕まづめに活性のピークを迎える。ベイトの動きを目視で追っているとされ、夜になり視界が悪くなるとともに活性が落ちていくが、常夜灯周りなど、ベイトが集まりポイントでは変わらず活性が高いケースも見られる。夜間は数は少ないものの大型が出やすい傾向にある。
◆タックル

◯ロッド
ヒラメ専用ロッドもあるが、シーバス用やショアジギングロッドがあれば流用が利く。サーフなど遠投が必要な釣り場では、10〜13ftでミディアムアクションのロッドがよい。ヒラメ狙いはラン&ガンでキャストと移動を繰り返していくため、軽くて高感度なティップにバットバワーのあるものがよい。足元から水深があるような港湾部ではあまり遠投の必要はないため、8〜9ftのミディアムアクションのシーバスロッド。水深があるポイントではメタルジグを使用することも想定して少し硬めのものがよい。
◯リール
ロッドとのバランスを考えると3000〜4000番のスピニングリールなら間違いない。50〜60㎝を超えるサイズになるとそのパワーと瞬発力に苦戦させられることもしばしば。なるべくドラグ性能のよいものを選択しよう。またサーフで使用することが多いので砂を噛んだり波をかぶってもメンテナンスしやすいものを選ぼう。
◯ライン
サーフでは遠投できるかどうかが釣果を大きく左右する。そのため飛距離を優先してPEラインを選択する。
PEラインは細ければ細いほど飛距離を延ばすことができるが、あまり細すぎると強度に不安が残る。せっかく大型のヒラメをヒットさせたのにラインが切れてバラしてしまったのでは後悔してもしきれないだろう。ビギナーならなおさらだ。1・2号から心配なら2号を巻いておこう。長さは200m巻ければ問題ない。
◯リーダー
ナイロンまたはフロロカーボンランの4〜5号を使用する。フロロの特性として根ズレに強い点が挙げられるが、この特性は岩礁帯や障害物の多いポイントのみならずサーフでも大きなアドバンテージとなる。砂で傷がつくことも多いのだ。
また、ヒラメには鋭い歯があり、小魚を噛みついてとらえる。そういった点でも歯ズレ(歯が触れて切れること)を防ぐうえにおいてもリーダーが必要となる。長さは60㎝〜3m。結束に自信がない人は結び目がガイドを通らないくらい短くしてもよい。
◆ルアー
主にミノーで、フローティングタイプもシンキングタイプも出番が多い。優先させたいのは遠投性と小魚に似たリアルなアクション。そのため水深の浅いサーフではフローティングミノーを多用し、遠くへ飛ばしたいときにはヘビーシンキングミノーを使うのが効果的。そのほか、メタルジグ、ワームを使う。
にごりが強いときは強い波動で魚を寄せる効果が見込めるバイブレーションなども有効。

シンキングミノー
◯ミノー
フローティングミノー、シンキングミノーの9㎝以上が中心。サイズの大きいものを使う理由は遠投性とアピール力に優れるからである。
水深があまりない遠浅のサーフやヒラメの活性が高いときはフローティングミノーが活躍する。
シンキングミノーは飛距離が出る重いものが多く、サーフなどで広範囲を探るのに適している。また、水深があるポイントや風が強いとき、波が高いときでもしっかりスイミングするのでビギナーにも使いやすい。
サーフから狙う場合はまずシンキングから始めれば間違いないだろう。
日中狙うならイワシカラーなどのナチュラル系、まづめから夜にかけてはアピールカラーがよい。

ジグヘッド

メタルジグ
◯メタルジグ
ベイトフィッシュのサイズが小さくミノーでは大きすぎるときに有効。遠浅のポイントでは横に引くことが多いためスイミングアクションに優れた細身のモデルが適している。
デイゲームであればフラッシングが強くブルーやグリーン入りのベイトカラーが効果的。20~40gを中心にセレクトしよう。

ワーム
◯ワーム
シャッドテールが細かく振動してアピールが大きい。ベイトフィッシュに合わせて大きめのものがよい。ジグヘッドが主流でヒラメ釣り専用モデルもあるほどである。ヒラメは下から食ってくることが多いため、フックが下向きのジグヘッドやトレブルフック付きのものがおすすめ。自重は、飛距離と遠投性を考えると14〜20gが好ましい。また、ヒラメ釣り用のダウンショットリグもある。
◆サーフでの狙い方
◯基本はただ巻き
フローティングミノーなどのプラグは基本的にただ巻きで可。狙いめとなるのが流れや地形変化のある場所。中でも実績が高いのが離岸流や潮目。
潮目とは、速さや塩分濃度が違う別々の流れがぶつかり合う境目のことである。海流が激しく動くため酸素濃度が高く、ベイトが溜まりやすいためヒラメがつく。離岸流とは左右から寄せた波が合流して大きな流れとなり、沖に向かって流れている場所である。ここもベイトが溜まりやすいためポイントになる。
ナブラやボイルが見られるときは速めに引くのがいい。そうでなければ表層を引いたあと、リフト&フォールでレンジを広く探るのが効果的だ。フローティングミノーからシンキングミノー、メタルジグとローテーションしながらレンジを下げていく。
意外と食ってくることが多いのが岸際である。ここは、小魚を追いつめるのに好都合な場所であり、ルアーの回収寸前にバイトしてくることが多々ある。だからルアーを岸に上げるまで気を抜かないことだ。


◯地磯・ゴロタでの狙い方
ヒラメ狙いはサーフのイメージが強いが、サーフと地磯が隣接したような場所も好ポイントとなる。
こういった根掛かりする恐れがあるところではフローティングミノーが活躍する。活性の高い個体は上層付近で食ってくることが多いため、浅いレンジだけを狙ってラン&ガンしても効率よく探ることができる。ワームで上層を探るならトレブルフック付きのジグヘッドを使えばフッキング率が上がる。フックが下向きのジグヘッドも有効だ。
ポイントは、ヒラメの着き場となるストラクチャーと流れの変化があるところ。岩礁帯に生息するヒラメは小魚を追って回遊する傾向も強いため、小魚が溜まるような場所でも出る。
小魚の居場所を探るには、浅場で広範囲にルアーをキャストするのが有効。小魚がいればルアーに驚いて散ることがしばしばあるからヒントとなる。また、海をよく観察すると、水の色が濃くなっているところに小魚が溜まっていたりする。
見切られないように少し速めのスピードで一定のレンジをキープしながら探っていこう。


◆知らないと損するテクニック

◯ダウンショットリグ
ボトムから浮かせて一定のレンジをきっちり探る場合は、ダウンショットリグを試してみよう。
ダウンショットリグとは、仕掛けの一番下にシンカーをつけて、リーダーの途中にフックとワームをセットしたものである。アンダーショットリグともいう。
ミノーやジグヘッドリグを使ってボトムから一定のレンジをしっかりトレースするにはかなりの熟練が必要である。その点、ダウンショットリグならシンカーを着底させてルアーを動かすだけで、きっかり一定のレンジを漂わせることができる。
また根掛かりの心配も低く、ポイントを集中して攻めることが可能になるのでビギナーにも打ってつけである。
釣り方も簡単。シンカーをボトムにつけたままズル引きでOK。細かいシャクリを連続で入れてコンコンと海底を叩くように引いてくる方法も有効だ。ヒラメ用に設計された専用のリグも販売されているので根掛かりを恐れず挑戦してみよう。

◯メタルジグで大遠投
近距離で反応が無い場合やポイントが遠い場合はメタルジグで遠投して探ってみる。
メタルジグを使う上で考慮すべきはウエイトである。軽すぎるメタルジグで深場を探るとなると、かなりゆっくり引かなければ浮いてしまう。逆に重すぎると速く巻く必要があり攻めにくい。適正スピードで引けるウエイトのルアーを選び、狙ったポイントからサーフの波打ち際や堤防の足元までしっかり探れるようにしよう。
メタルジグのリトリーブスピードは基本的にスローでボトムから1mまでをトレースしながら引いてくる。
狙いのレンジを引けているかわからないときは時々リトリーブを止めてルアーが着底するまでの時間をカウントしてみよう。その時間に差が無ければレンジが一定の証拠である。
活性が高いときはストロークの長いリフト&フォールも有効。一旦着底させ、軽くジャークさせながらリフトしてルアーの存在をアピール。テンションを保った状態でフォールさせる。この繰り返しでバイトを誘う。フックをフロントアシストのみにすると根掛かりしにくいのでおすすめだ。
*監修 西野弘章【Hiroaki Nishino】
*編集協力 加藤康一(フリーホイール)/小久保領子/大山俊治/西出治樹
*魚体イラスト 小倉隆典
*仕掛け図版 西野編集工房
*参考文献 『週刊 日本の魚釣り』(アシェットコレクションズ・ジャパン)/『日本産魚類検索 全種の同定 中坊徹次編』(東海大学出版会)/『日本の海水魚』(山と渓谷社)/『海釣り仕掛け大全』(つり人社)/『釣魚料理の極意』(つり人社)